「スケボーって若者の遊びでしょ?」なんて思っていませんか?実は今、40代・50代からスケートボードを始める“おじさんスケーター”が増えているんです。
忙しい毎日の中で、ちょっとしたスリルと達成感を味わえるスケボーは、大人にこそぴったりの趣味。なかでも基本トリックの「オーリー(OLLIE)」は、誰もが最初にぶつかる壁でありながら、乗り越えたときの喜びは格別です。
とはいえ、「体力が落ちてるし…」「ケガが怖いな…」という不安もありますよね。でも安心してください。このブログでは、40~50代のスケボー初心者でも無理なく安全にオーリーをマスターするためのコツと練習法を、わかりやすく丁寧に解説していきます。
いくつになっても挑戦し続けるおじさんはかっこいいですよね。 新しいことにチャレンジする勇気が、日々をもっと楽しく、充実したものにしてくれます。
このブログを通して、あなたのスケボーライフが最高にワクワクするものになりますように。それではさっそく、「オーリーとは何か?」という基礎から始めていきましょう!
スケボー未経験でも安心!オーリーを始める前に知っておきたい基礎知識
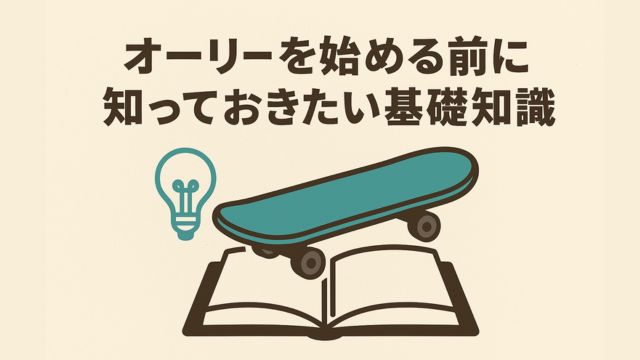
スケボー初心者にとって最初の壁となるのが、なんといっても「オーリー」です。見た目はシンプルなのに、いざやってみると「どうやって跳ぶの?」と戸惑ってしまう人も多いのではないでしょうか。
ですが安心してください。オーリーにはちゃんとした仕組みがあり、それを理解すれば体の動きも自然とついてきます。
ここでは、まずオーリーという技がどのような原理で成り立っているのかを、誰にでもわかるように解説していきます。
オーリーは「テコの原理」で跳ぶ技
オーリーとは、スケートボードの基本トリックの一つで、ジャンプするようにデッキを浮かせる技術です。
見た目はシンプルに見えるかもしれませんが、実は「テコの原理」を活用した高度な体の使い方が求められる動作なんです。
テコの原理とは、「支点・力点・作用点」の3つの要素で構成される仕組みです。小さな力で大きな物を動かす原理であり、スケボーではこれがそのまま応用されています。
具体的には、スケートボードの後ろのウィール部分が“支点”、後ろ足でテールを蹴る部分が“力点”、そして前方に跳ね上がるノーズが“作用点”となります。
この仕組みによって、板は斜め上に浮き上がります。そこから前足でノーズを押さえ、体を引きつけることで、空中でデッキを水平に保ちます。
まずはこの“テコの原理”という視点からオーリーを見てみることで、これまで「なんとなく」でやっていた動作にも納得がいくはずです。
スケボーを始めるおじさんが知っておくべき用語
スケートボードをこれから始めるにあたって、まず覚えておきたいのが「基本用語」です。若いスケーターたちは当たり前のように使っている言葉でも、初めて聞くと「それ、どういう意味?」と戸惑ってしまうこともあります。
特に40~50代のおじさん世代では、道具選びや練習方法をネットや動画で調べることが多いため、用語を知っているかどうかが理解のしやすさに大きく関わってきます。
オーリーの練習やスケボーライフを楽しむうえで、最低限知っておきたい基本用語をまとめました。
スケートボード基本用語
- デッキ(Deck):スケートボードの板部分。主に7層の木材でできており、足を乗せるところ。
- テール(Tail):デッキの後ろ側。オーリーではここを後ろ足で弾いてジャンプします。
- ノーズ(Nose):デッキの前側。オーリーでは前足でここを押さえて板を平行にします。
- ウィール(Wheel):スケボーのタイヤ。硬さや大きさで乗り心地が変わります。
- トラック(Truck):デッキとウィールをつなぐ金属パーツ。ターンのしやすさを左右します。
- スタンス(Stance):スケボーに立つときの足の位置。オーリーには正確なスタンスが必須です。
- ビス(Bolt):デッキとトラックを留めているネジ。前後の位置を見分ける目印にもなります。
基本用語を知っておくことで、動画解説やスケーター同士の会話もスムーズに理解できるようになります。また、スケボーショップで店員さんと話すときにも、自分に合った道具を選びやすくなりますよ。
知らないことは決して恥ずかしいことではありません。最初は「これ、なんのこと?」と思うのが当たり前。ですが、一つひとつ意味を理解していくことで、スケボーの世界がどんどん身近になっていきます。
道具の名前から足の置き方まで、基本用語をしっかり覚えて、オーリー習得に向けた第一歩を踏み出しましょう!
40代からのスケボーは何に気をつけるべきか?
スケートボードは若者のスポーツというイメージがありますが、実は40代、50代になってから始める方も年々増えています。
スケボーは全身運動であり、楽しみながら体力やバランス感覚を鍛えることができるので、中年世代の健康維持にもぴったりです。
とはいえ、年齢を重ねてから始めるからこそ、気をつけるべきポイントもいくつかあります。無理をせず、体の声を聞きながら、安全に楽しむことが何より大切です。
まずひとつ目は、ウォームアップを怠らないこと。若い頃と違い、関節や筋肉の柔軟性が低下しているため、いきなり動き始めるとケガのリスクが高まります。
ストレッチや軽いジャンプ運動などで体を温めてからボードに乗りましょう。
次に重要なのが、プロテクターの着用です。特にヒジ・ヒザ・手首のガードは必須アイテム。転倒時のダメージを大きく軽減してくれるので、安心して練習に集中できます。ヘルメットも忘れずに着けましょう。
また、無理な練習をしないこともポイントです。調子が良いとつい長時間滑ってしまいたくなりますが、体力の限界を越えるとケガにつながります。「今日はここまで」と線を引けることが、大人スケーターの心得です。
そして、焦らずマイペースで。周りの若いスケーターが上手にトリックを決めていても、自分のペースを守ることが大切です。練習に時間がかかっても、少しずつできるようになる過程を楽しみましょう。
最後に、楽しくやることを忘れずに。失敗しても笑える、上達すれば嬉しい。そんな気持ちで続けることが、長く楽しむコツです。
「40代だからこそ、今が始めどき」。そう思って、無理なく、でもしっかりと一歩ずつオーリーの習得を目指していきましょう。
スケートボードとシューズの選び方のポイント
スケボーを始めるうえで、最初につまずきやすいのが「道具選び」です。特にデッキ(板)やシューズは、オーリーのやりやすさや安全性にも直結する重要なポイント。
40~50代のおじさんスケーターにとっては、体への負担が少なく、操作しやすい道具を選ぶことが、上達への近道になります。
まずはスケートボード(デッキ)の選び方です。初心者におすすめなのは、幅が8.0インチ程度のデッキ。
幅が広めで安定感があり、体重があってもブレにくいため、年齢を重ねた方でも安心して扱えます。ブランドにこだわる必要はありませんが、できればスケートボード専門ショップで購入するのが安心です。
次にシューズですが、これは「スケートシューズ」と呼ばれる、専用の靴を選ぶのが鉄則です。
スニーカーではダメなの?と思うかもしれませんが、スケートシューズはソールがフラットでグリップ力が強く、デッキとの一体感が全然違います。
ソールが分厚すぎる靴や、エアクッション付きのジョギングシューズは不安定になりやすく、逆に危険です。
また、スケートシューズは履き心地も大切です。おじさん世代は足に合わない靴を無理に履くと膝や腰に負担がかかります。
購入前に必ず試し履きをし、かかとがしっかりホールドされ、つま先が自由に動かせるものを選びましょう。
おすすめのスケートシューズブランドには、「Vans(ヴァンズ)」「Nike SB(ナイキSB)」「adidas Skateboarding(アディダス)」「eS(エス)」などがあります。
どれもスケーターからの評価が高く、耐久性と機能性が優れているので安心して選べます。
スケートボードとシューズは、あなたの“相棒”となる大切な存在。長く楽しく続けるためにも、最初から妥協せず、自分に合った道具をしっかり選ぶことが大切です。
練習前に必須!安全対策と心構え
スケートボードを始めるときに絶対に忘れてはいけないのが、「安全対策」と「心構え」です。特に40〜50代のおじさん世代にとっては、若い頃と違って無理が利かない分、事前の備えがケガのリスクを減らし、より長くスケボーを楽しむためのカギになります。
まず安全対策として必ず身につけたいのが、ヘルメット・ヒザパッド・エルボーパッド・リストガードの4点セットです。
スケボーはバランスを崩して転倒するスポーツです。特にオーリーのようにジャンプを伴うトリックでは、初めのうちは必ず転びます。それ自体は悪いことではありませんが、守るべき部分を守っておかないと、大きなケガにつながります。
また、服装も大事です。できれば厚手の長袖・長ズボンを着用しましょう。転倒時のすり傷を軽減できますし、肌の露出が少ないことで安心感もアップします。
夏場は熱中症に注意しながら、通気性の良い素材を選ぶといいでしょう。
次に大切なのが心構えです。大人になってから新しいことに挑戦するのは、勇気がいること。でも、最初から完璧にできる必要なんてありません。
失敗しても恥ずかしくない。むしろ「挑戦している自分」がすでにかっこいいんです。
「今日は転んでもいいから3回テールを弾いてみよう」など、小さな目標を設定することが大切です。
そして、楽しむ気持ちを常に忘れないこと。失敗しても「今のは惜しかったな」「もう少しでできそう」とポジティブに捉えることで、モチベーションも維持できます。
いくつになっても挑戦し続けるおじさんはかっこいいですよね。ケガをしないように対策をしっかりとりながら、「やってみたい」という気持ちを大切にして、安心・安全なスケボーライフのスタートを切りましょう!
オーリー完全攻略!動作を5ステップで分解解説

オーリーの動作はすべてがつながっていて、1つのミスが全体に影響します。ここでは「スタンスから着地まで」を5つのステップに整理し、それぞれの動きと体の使い方を明確に解説します。
特に中年世代に必要な“理論的な理解”を重視した構成です。
ステップ①:正しいスタンスと重心をセットする
後ろ足はテールの端の中央に、前足は前ビスの少し手前に置きます。重心は両足の真ん中に置き、姿勢を安定させましょう。このとき、背中を丸めず、お尻を軽く引き上げるような意識で“真上に跳ぶ準備”を整えます。
ステップ②:すり足を先行しながらテールを弾く
前足のすり足をわずかに先行させて、重心を“抜く”感覚を作った直後、後ろ足でテールを下方向に「パチン」と強く弾きます。これがオーリーのジャンプを生み出す力の源。すり足が先行することでデッキが浮きやすくなります。
ステップ③:すり足の足首を戻してノーズを平行にする
すり足で寝かせていた前足の足首を元に戻すことで、ノーズが進行方向と水平になり、デッキが安定します。この動作がデッキの“平行”を作り出し、板が自然と体にフィットするようになります。
ステップ④:テールが上がると同時に後ろ足を引きつける
ノーズを前足で押さえたことで、テール側が上がってきます。このタイミングで後ろ足を上へ引きつけるようにして、デッキと体の一体感を高めます。後ろ足は板に添えるように自然に動かしましょう。
ステップ⑤:デッキを保ち四輪で同時着地する
空中で体の軸をキープしたまま、前足と後ろ足の高さを調整してデッキを平行に保ちます。着地時は四輪すべてが同時に接地するよう意識し、膝を柔らかく使って衝撃を吸収。スムーズで安定した着地が完成です。
スタンスの取り方と足の位置を正しく理解しよう

オーリーを成功させる第一歩は、正しいスタンスと重心のセットです。足の位置だけでなく、姿勢と重心が整っていないと、その後のジャンプやデッキのコントロールに大きく影響します。
後ろ足はテールキックの中央に、つま先の付け根(母指球)を置くのがベストポジションです。ここがデッキを弾くときに最も力が伝わりやすいポイント。
前足は前ビスの手前あたりにセットし、両足ともデッキの中央ラインに沿うように意識しましょう。
重心は両足の中間に置きます。やや前足寄りでも構いませんが、頭や体が左右にぶれないよう、まっすぐ立つことが重要です。
さらに、お尻を軽く持ち上げるように準備姿勢をとることで、ジャンプに必要な伸び上がる力を引き出しやすくなります。
目線は前方のビスを見て、体のバランスを整えましょう。この基本姿勢を正しく身につけることで、次の動作がスムーズになり、オーリーの成功率が格段に上がります。
すり足を先行しながらテールを弾く

オーリーで重要なのは「すり足を先行させてからテールを弾く」動作の連携です。まずはすり足を軽く先に動かすことで、体の重心がデッキから一瞬“抜ける”感覚をつくりましょう。
その瞬間に後ろ足でテールを真下に「パチン」と弾きます。
このタイミングが絶妙であれば、デッキがきれいに跳ね上がり、自然と空中に浮き上がります。「すり足が先」「テールが後」ではなく、ほぼ同時に重なるイメージを持つと効果的です。
力任せではなく、正しい位置とタイミングで弾ければ、「パチン!」と気持ちの良い音が鳴るはずです。この音を目安に、自分の動作が正しくできているか確認しながら練習を重ねましょう。
前足を上半身に引きつける

テールを弾くと同時に、膝を前に出すように上半身に引きつけます。膝を前に出すことにより足首が自然に寝ます。この動作がすり足と呼ばれています。この引き上げにより、オーリーの高さが決まります。
空中で寝ている足首を膝から下だけを意識して元に戻す動作と連動させて後ろ足も上げていくと、デッキが平行になります。この時、重心は安定させるために、頭の位置を動かさないことがポイントです。
力で押すのではなく、軽く戻す感覚でOKです。このとき、体の重心が崩れていなければ、自然とデッキは体と平行になっていきます。
テールが上がると同時に後ろ足を引きつける

寝ているすり足を元に戻すと同時に、テールが上がってくるタイミングに合わせて、後ろ足を上方向へ引きつけます。
この動作がしっかりできると、板全体が体に密着し、空中でのコントロールが格段に向上します。
無理に持ち上げようとせず、自然に膝を引き上げることで、スタイリッシュで安定したオーリーが実現できます。
練習は裏切らない!おじさん向けオーリー上達のための練習メニュー

オーリーを習得するためには、正しいやり方だけでなく、効率的な練習方法を知ることも重要です。ここでは、40〜50代の大人世代でも無理なく続けられる、現実的な練習メニューや練習の工夫を紹介します。
自分のペースで、着実にレベルアップしていきましょう!
止まった状態から始めるのが上達の近道
オーリーの練習を始めるとき、多くの人が「スピードをつけないとできないんじゃ?」と感じるかもしれません。
確かにスムーズに滑っている方が勢いを利用しやすく見えますが、40〜50代の初心者には「止まった状態」からの練習をおすすめします。
理由はシンプルで、安全かつ動作の確認がしやすいからです。スピードがあると、転倒したときのダメージも大きく、フォームの細かい部分に意識が向かなくなりがちです。
まずは焦らず、その場で動かずに「オーリーの型」を固めることが、結果として上達を早めます。
止まった状態での練習では、ひとつひとつの動作を丁寧に確認できます。足の位置、膝の使い方、テールの弾き方、前足の擦り上げなど、それぞれの工程をしっかり意識して体に覚えさせることが大切です。
また、この練習を行う場所にも工夫を。芝生やカーペットの上で練習すると、ボードが転がらず安定するので、オーリーの動作に集中しやすくなります。自宅の庭や公園の隅、またはインドア用のスケートスペースがあれば最適です。
止まった状態での練習では、成功・失敗がすぐに分かりやすく、修正もしやすいのがメリット。例えばテールを強く弾いたのに音がしなければ力の入れ方や位置を見直せばいいし、板が浮かないなら重心がズレている可能性を考えられます。
「止まったままだと意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。プロスケーターでさえ、トリックの確認を止まった状態で行うことはあります。
それだけ基本動作の反復が重要だということです。
まずは安全な場所で、止まった状態からコツコツと練習を積み重ねていきましょう。いずれスピードに乗せたときでも、ブレないフォームが自信と安定感を生み出してくれます。
物に掴まって練習するメリット・デメリット
オーリーの練習を始めたばかりのとき、「手すりや壁など、何かに掴まりながら練習したほうがいいのでは?」と考える方も多いと思います。実際、物に掴まって練習するのは、初心者にとって安心感があり、恐怖心を和らげる方法のひとつです。
特に40~50代のおじさんスケーターにとって、転倒のリスクを減らせるという点では大きなメリットがあります。バランスを崩したときでも、即座に掴まれる安心感があるため、思い切ってテールを蹴ったり、前足を高く引き上げたりと、動作に集中しやすくなります。
また、動作そのものを分解して覚える際にも効果的です。たとえば、オーリーの「テールを弾く」部分や「前足をすり上げる」部分だけを、手すりに掴まりながら練習することで、足の動きに集中しやすくなるという利点もあります。
ただし、物に掴まった練習にはデメリットも存在します。もっとも大きいのは、重心コントロールや上半身の動きが実際とは異なるという点です。掴まっている分、上半身が固定されてしまい、本来オーリーで必要となる「軸の安定」や「体全体でデッキを扱う感覚」が身につきにくくなるのです。
そのため、掴まりながらの練習はあくまでも「一時的な補助」として捉えましょう。最初の数日間で基本的な動作を確認するには有効ですが、なるべく早く手を離した状態での練習に移行することが重要です。
補助練習は「怖さを乗り越えるための第一歩」。自転車の補助輪と同じように、慣れてきたら手放しでチャレンジする勇気が上達へのカギです。最終的には、自分の体一つでバランスを取りながらオーリーを決められるようになることを目指しましょう。
自分の成長を記録!動画撮影でフォーム分析
オーリーの上達において、意外と見落とされがちですが、効果的なのが動画撮影です。自分の動きを客観的に確認できることは、練習の質を大きく高めてくれます。
特に、体の動かし方に意識を向けづらい40〜50代の初心者にとっては、自分のフォームを「見える化」することが、改善の近道になります。
普段、自分がどんなふうにジャンプしているのか、テールをどれくらい強く蹴っているか、前足のすり足はしっかりできているか…練習中はなかなか意識が回らないポイントも、動画で見返すと一目瞭然です。
スマホを三脚に固定したり、地面に置いたりして、側面からの角度で撮影するのがポイントです。最初は照れくさいかもしれませんが、1回撮って見てみると、「あ、なるほど」と気づくことが本当に多くあります。
動画撮影のもう一つの利点は、自分の成長が記録として残ることです。今日できなかった動作が、1週間後には少しできている。1ヶ月後にはスムーズになっている。
その変化を自分の目で確認できることは、大きなモチベーションになります。
さらに、SNSにアップすることで、同世代のスケーター仲間と交流が生まれることもあります。コメントでアドバイスをもらえたり、「頑張ってますね!」と声をかけてもらえたりするだけで、「また練習しよう!」という気持ちになれるものです。
分析の視点としては、次のようなチェック項目を意識して動画を見ると効果的です:
- ジャンプとテールを弾くタイミングが合っているか?
- デッキがしっかり浮いているか?
- 前足のすり足が板に沿って動いているか?
- 空中でデッキが平行になっているか?
- 着地時に重心がブレていないか?
記録は「自分へのフィードバック」であり、「過去の自分との比較対象」でもあります。動画撮影は、楽しみながら成長を実感できる、まさに現代ならではの練習法。
ぜひ活用して、効率よくオーリーをマスターしていきましょう!
スケジュール例:週3回・15分で上達する方法
オーリーの習得において大切なのは「継続して練習を続けること」です。ただ、仕事や家庭の時間でなかなかまとまった時間が取れない…という方も多いですよね。特に40~50代のおじさんスケーターにとって、体力的にもスケジュール的にも「毎日2時間練習!」というのは現実的ではありません。
そこでおすすめなのが、週3回・1日15分という無理のないスケジュールです。短時間でも、内容をしっかり絞って集中して取り組めば、着実に上達していけます。むしろ、ダラダラ長く練習するより、短くても集中した練習のほうが効果的です。
以下に、1回15分のおすすめ練習メニューの例をご紹介します。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 0〜3分 | ストレッチ+ウォームアップ(軽いスクワットや足首回し) |
| 3〜5分 | スタンス確認+テールを弾く動作の反復 |
| 5〜10分 | オーリーの動作を分解して反復練習 |
| 10〜13分 | 1回のオーリーをフルで実施→動画撮影やフォームチェック |
| 13〜15分 | クールダウン、軽いストレッチ、今日の振り返り |
このように、1回の練習を「ただ滑る」だけで終わらせず、具体的な動きに分解して確認しながら進めるのがポイントです。特に社会人の方は「今日は5分だけでもOK」と自分に許すことで、継続のハードルがグッと下がります。
そして、週3回続けることで徐々に体が動きを覚え、動作の精度も上がっていきます。「なんとなく感覚がわかってきたな」という実感が持てると、モチベーションも自然と上がっていくはずです。
短くてもいい、でもやめないことが大切。あなたのペースで、無理なく、でもしっかりと続けていきましょう。
障害物を飛ぶ練習法とオーリーバーの活用術
オーリーがある程度形になってきたら、次のステップとして挑戦したいのが「物を飛ぶ練習」です。フラットで板を浮かせるだけのオーリーと、障害物を越えるオーリーでは、必要な感覚やタイミングが違ってきます。
まずは低い障害物から始めましょう。例えば、割り箸やペットボトルのような「失敗しても怖くない物」がおすすめです。これを飛び越える練習をすることで、「目標を超える」という意識が生まれ、自然と前足の引きつけやタイミングが磨かれます。
次のステップでは、ホームセンターなどで購入できるパイロン(コーン)を活用しましょう。1個のコーンから始めて、2つ重ねる「セットコーン」で高さ約30cm、さらにバー(トラ棒)を乗せれば最大60cm程度まで調整できます。
このとき役立つのがオーリーバーです。市販のものでも自作のものでもOKで、2つのコーンの間にバーを渡すだけで「安全な障害物」が作れます。落ちても壊れにくく、板に絡まない構造なので、思い切って挑戦できる環境が整います。
オーリーバーを使うことで、自分のオーリーの高さや幅が「見える形」で確認できるようになるのもメリット。バーを徐々に高くしていくことで、段階的にスキルアップできます。
さらに、障害物を飛ぶ練習では目線とスピードの使い方がポイントです。目線は飛び越える「物の一番高い部分」を見るようにし、スピードは最初はゆっくりでOK。慣れてきたら徐々にスピードを上げていくと良いでしょう。
オーリーバーやコーンを使った練習は、成功したときの達成感が非常に大きく、モチベーションの維持にもつながります。飛べなかったものが飛べた瞬間、自信もグッとアップしますよ。
怪我のリスクを抑えつつ、実践的な技術を身につけるには、この「障害物越え練習」は欠かせません。ぜひ楽しみながら取り入れていきましょう!
失敗して当たり前!オーリーでつまずきやすいポイントと対策

どんなスケーターも、最初から完璧にオーリーができるわけではありません。つまずきやすいポイントを知り、適切な対処法を取ることで、挫折せずに上達への道を進むことができます。
このセクションでは、よくある失敗例とその乗り越え方を解説していきます。
テールがうまく弾けない原因と修正法
オーリー練習で最初につまずきやすいのが「テールをうまく弾けない」という問題です。
思い切って蹴っているつもりなのに、デッキがほとんど浮かばなかったり、「パチン」という音が鳴らなかったりすると、自信もなくなってしまいますよね。
しかし、ここで知っておいてほしいのは、これは誰もが最初に通る道だということ。むしろ、ここで原因をしっかり把握して修正できるかどうかが、その後の上達を大きく左右します。
まず考えられる原因のひとつは、足の位置が適切でないことです。後ろ足のつま先がテールの端の中央から外れていると、力がうまく伝わらず、しっかり弾くことができません。
特に親指の付け根(母指球)でテールを押し込むようにすることで、安定して力を加えることができます。
次に多いのが、重心が後ろすぎるケースです。ジャンプしようとするあまり、体が後ろに反ってしまうと、テールを蹴る前にバランスを崩してしまいます。
重心は常にデッキの中央からやや前に置くように意識してみましょう。
また、蹴るタイミングが遅れている場合もあります。テールは「ジャンプするのと同時に真下に弾く」ことで、うまく反発力が生まれます。
動作がバラバラになっていると、板が地面に当たる勢いが足りず、浮きも音も弱くなってしまうのです。
解決策としては、スタンスとタイミングを重点的に確認しながら、止まった状態で反復練習するのが効果的です。
「パチン」と良い音が鳴るまで蹴りの強さや角度を少しずつ調整していきましょう。音が出始めれば、蹴りのコツが掴めてきた証拠です。
動画撮影もおすすめです。自分ではしっかり蹴っているつもりでも、映像で見ると全然蹴れていない…というのはよくある話。視覚的なフィードバックを得ることで、より早く修正ができます。
焦らず、でもしっかりと基本を繰り返すことで、必ずテールは思い通りに弾けるようになります。「うまくいかない=才能がない」ではありません。「正しい方向に練習できているかどうか」がすべてです。
スライドが決まらないときは靴と姿勢を見直そう
オーリーの練習を進めていると、「テールは弾けるようになったけど、前足のスライド(すり足)が全然決まらない…」という壁にぶつかる人が非常に多いです。
このすり足の動作ができないと、デッキが空中でうまく浮かび上がらず、オーリーに高さが出ません。
まず確認すべきは、靴の状態です。スケボー専用のスケートシューズを履いていないと、足がデッキにうまく引っかからず、滑るように感じたり、摩擦が足りずスライドができなかったりします。
スケートシューズはソールがフラットで柔らかく、グリップ力が強いのが特徴です。
もし「普通のスニーカーで練習している」という場合は、VansやNike SB、adidas Skateboardingなどのスケートシューズを試してみてください。
足元の感覚が変わるだけで、スライドの動作がぐっとやりやすくなります。
次にチェックすべきは姿勢と足首の角度です。すり足は、前足を「ただこする」だけではなく、寝かせた足首を戻す動作と連動させることでスムーズに滑らせることができます。
このとき、前足のつま先がやや内側に向いていると、板にしっかり接触しやすくなります。
また、上半身が前傾しすぎていると、足の動きが制限され、すり足が途中で止まってしまうことがあります。背筋を軽く伸ばし、重心をやや前足寄りにキープすることで、前足が自然と動きやすくなります。
スライドの動きは、はっきり言って「感覚」がものを言う部分です。しかしその感覚を育てるためには、正しい装備と姿勢が必要不可欠です。うまくいかないと感じたときは、道具と体の使い方を今一度見直してみてください。
「道具のせいにしちゃダメ」と思う人もいるかもしれませんが、実際には道具を見直すことでブレイクスルーが起きることは少なくありません。
しっかり準備を整え、体に優しい姿勢でコツコツと感覚を磨いていきましょう。
板が足についてこない!その理由と対処法
オーリーの練習を重ねる中で、「ジャンプはできたけど、デッキだけが置いてけぼりになってしまう…」という経験をしたことはありませんか?
これは初心者にとても多い悩みであり、いくつかの原因と明確な対処法があります。
まず考えられるのは、ジャンプとテールを弾く動作がバラバラになっていることです。体がジャンプする前にテールを弾いてしまうと、デッキの上昇を足が邪魔してバタバタしてしまいます
逆にジャンプのあとで弾いてもタイミングが遅く、デッキだけが置いてけぼりになってしまいます。
この場合は、「ジャンプとテールのキックを同時に行う」という基本をしっかり意識して練習しましょう。空中で体とデッキが一体になるためには、このタイミングの一致が不可欠です。
次に見直したいのが、重心の位置です。ジャンプ時に重心が後ろ足に偏っていたり、逆に前に突っ込みすぎていたりすると、体と板の動きがバラバラになります。
理想は体の中心が常に板の中央ラインの上にあること。この姿勢を保つだけで、デッキが体に“ついてくる”感覚が出てきます。
また、すり足が中途半端になっていると、板にしっかりと引っかからず、空中で足から離れてしまいます。特に膝を上げる意識が弱いと、デッキが浮ききらず「ついてこない」現象が起きやすいです。
対策としては、次のような点を意識して練習してみてください:
- ジャンプと同時にテールを弾く
- すり足は「こする」よりも「膝を上にあげる」イメージ
- 体を真上に伸ばし、頭の位置をぶらさない
- 着地まで重心を安定させる
このように、板が足から離れてしまうのは「力が足りない」のではなく、タイミングと重心の問題であることがほとんどです。
焦らず丁寧に、自分の動きを動画でチェックしながら、原因をひとつずつ潰していくことが成功への近道です。
正しい動作が身についてくると、ある日突然「あれ?ついてきた!」という感覚を得られます。それが、あなたのオーリーが“つながった”証拠です。
怖さが先に立つときの心構えと対処法
オーリーの練習で多くの人がぶつかる最大の壁、それが「怖さ」です。頭では「ジャンプしてテールを弾くだけ」とわかっていても、体が言うことを聞かない。「転んだらどうしよう」「失敗したら恥ずかしい」そんな不安が、動きを止めてしまいます。
特に40〜50代の方にとっては、体力の衰えやケガへの不安も加わり、この“怖さ”が行動のブレーキになりがちです。
でも大丈夫。この怖さを感じること自体が、真剣に取り組んでいる証拠。大人だからこそ慎重になるのは自然なことです。
まず大事なのは、怖さを否定しないこと。「こんなことでビビってる自分はダメだ」と責めるのではなく、「今はまだ怖くて当然」と受け入れるところからスタートしましょう。
気持ちが楽になれば、動きにも少しずつ余裕が生まれます。
次に効果的なのが、段階的なステップで練習すること。いきなりオーリーを決めようとせず、まずは止まった状態でテールを「パチン」と弾く練習から始めましょう。
成功体験を積み重ねることで、自然と怖さは薄れていきます。
また、安全対策をしっかり行うことも重要です。ヘルメットやプロテクターを着用すれば、「転んでも大丈夫」という安心感が生まれ、思い切って動けるようになります。環境を整えることが、心のブレーキを外すきっかけになるのです。
そしてもうひとつ、「上手くできなくても楽しい」という気持ちを忘れないこと。オーリーが失敗しても、「今日はここまで頑張った!」と自分を認めてあげることが、継続のモチベーションにつながります。
最後に、目線を少し先に向けることも有効です。「今できること」に集中しつつ、「1ヶ月後にはこれくらいできていたい」という希望を持つことで、不安よりもワクワクが勝ってきます。
怖さを感じるのは挑戦している証拠。いくつになっても挑戦し続けるおじさんはかっこいいですよね。その一歩を踏み出したあなた自身を、ぜひ誇りに思ってください。
後ろ足が寝ない?空中姿勢の作り方を解説
オーリーの上達を目指す中で、動画や上級者の動きを見て「なんであんなにデッキと体が一体になってるの?」と思ったことはありませんか?
特に印象的なのが、空中で後ろ足が“寝ている”ようなスタイル。(刺しオーリー)この姿勢は見た目にもかっこよく、オーリーの完成度をグッと高めてくれます。
しかし実際にやってみると、「自分の後ろ足がうまく寝てくれない」「空中でバランスが崩れる」と感じる方がほとんど。
それもそのはずで、この“寝かせる動き”は単に足の角度だけで作るものではなく、全体の空中姿勢と重心のコントロールがポイントなのです。
まず意識したいのが、空中での重心の固定です。ジャンプしたあと、頭と上半身の位置をできる限りブレさせず、空中で体の「軸」を保つようにします。
これができていると、自然と体全体が安定し、後ろ足を自由に動かしやすくなります。
そして、前足をしっかりと前方にスライド&引きつけることで、ノーズが持ち上がり、それにつられて後ろ足が自然に寝たような形になります。
足だけを寝かせようとするのではなく、前足で“形を作る”という意識のほうが成功しやすいです。
具体的な動作としては、空中で足首の角度を軽く内側に倒しながら、膝も一緒に引き上げることで、板全体の傾きがコントロールできます。
そしてこのとき、後ろ足は板に軽く添えるようにキープ。無理に引き上げるのではなく、あくまでも自然な流れで“寝かせる”のがポイントです。
注意点としては、この動きはオーリーにある程度慣れてから取り入れるようにしましょう。基礎が固まっていない段階で無理にフォームを意識すると、バランスを崩したり、怪我の原因になってしまうことがあります。
まずは、基本のオーリーをしっかり身につけた上で、「板と体を一体化させる意識」を持ちながら練習していくことで、少しずつ空中姿勢も美しく整っていきます。
見た目もかっこよく、技術的にも洗練された“刺しオーリー”を目指して、一歩ずつステップアップしていきましょう。
楽しみながら続けよう!おじさんのためのスケボーライフのすすめ

オーリーの練習はもちろん大切ですが、スケボーの魅力はそれだけではありません。趣味としての楽しみ方や、仲間や家族とのつながりを通じて、スケートボードは人生をより豊かにしてくれます。
このセクションでは、長く楽しく続けるための工夫とスケボーライフの魅力をご紹介します。
スケボーで運動不足を解消しよう
40〜50代になると、仕事中心の生活で体を動かす機会がぐんと減り、「最近ちょっとお腹が出てきたかも…」と感じる方も多いのではないでしょうか。そんなおじさん世代にこそおすすめしたいのが、スケートボードです。
スケボーは一見トリック中心の若者の遊びに見えますが、実は全身運動のかたまり。足腰の筋力はもちろん、バランス感覚、体幹、そして反射神経まで、体のあらゆる部分をフルに使うスポーツなんです。
例えばオーリーを練習するだけでも、ジャンプに必要な大腿四頭筋やハムストリングス、そして着地時の衝撃を吸収するふくらはぎ・ヒザ周りの筋肉がしっかり使われます。
しかもトリックを繰り返すことで、有酸素運動としての効果も期待できるため、脂肪燃焼や基礎代謝アップにも効果的です。
さらに、スケボーは楽しみながらできる運動という点が大きな魅力です。ウォーキングや筋トレと違い、「やらなきゃいけない」ではなく、「やりたいからやる」運動になるので、長続きしやすいんですね。
「毎日30分滑る」ではなくても、「週末に1時間、公園でのんびりスケボーを楽しむ」だけで十分。日常の中に気軽に取り入れることで、自然と運動量が増え、健康維持にもつながるはずです。
もちろん無理は禁物。最初は短時間からスタートして、徐々に体を慣らしていきましょう。ストレッチを取り入れたり、休憩をこまめに取ったりすることで、怪我の予防にもなります。
「体を動かしたいけど、何をすればいいかわからない…」という方は、ぜひスケートボードに挑戦してみてください。気づけば、運動不足の解消どころか、趣味としてもどっぷりハマってしまうかもしれませんよ!
目標を決めてモチベーションを維持しよう
スケボーは「練習すればするほど上手くなる」スポーツですが、40〜50代になると体力や忙しさもあり、ついつい継続が難しくなってしまうことも。
そんなときに大切なのが、自分なりの“目標”を持つことです。
目標といっても、大きなことである必要はありません。「今月中にオーリーで板を浮かせる」「来週末までにテールを強く弾く感覚をつかむ」といった、小さな達成目標で十分。
それを一つひとつクリアしていくことが、自信となり、継続の原動力になります。
人は目的があると努力できます。「何となく」滑るよりも、「この練習を〇〇のためにやっている」という意識を持つことで、集中力や成果の出方も変わってくるのです。
また、目標は「技術面」だけでなく、「生活面」や「気持ちの面」でもOKです。
たとえば「ストレス発散のために週に1回滑る」「息子にかっこいいところを見せたい」「健康のために1日15分動く」など、自分だけのモチベーションを持つことが大切です。
さらにおすすめなのが、練習ノートやSNSで目標を記録する方法です。練習日記に「今日の目標」「できたこと」「次回やること」をメモするだけでも、振り返りができて成長を実感しやすくなります。
SNSでは、同じようにスケボーを頑張っている仲間と繋がれることも。共通の目標を持った人がいるだけで、「自分もがんばろう!」という気持ちが湧いてきます。
年齢に関係なく、目標を持って取り組む姿は本当にかっこいいものです。いくつになっても挑戦し続けるおじさんはかっこいいですよね。
自分だけのゴールを設定して、スケボーライフをもっと楽しく、もっと充実させていきましょう!
インスタやYouTubeでスケボーライフを共有
せっかくスケボーにチャレンジしているなら、その過程や成果をインスタグラムやYouTubeで発信してみませんか?最近は40~50代の“おじさんスケーター”もSNSでどんどん情報を発信し、仲間とつながる時代です。
「動画なんて恥ずかしい」と思うかもしれませんが、最初は自分の記録用でもOKです。練習の様子をスマホで撮って保存するだけでも、成長の過程が見える化でき、自信にもつながります。
特にインスタグラムでは、#おじさんスケーター #スケボー練習記録などのハッシュタグを使えば、同世代のスケーターと簡単に交流できます。
「いいね!」やコメントで応援されると、それだけで次の練習のやる気がアップしますよ。
YouTubeもおすすめです。短い動画でもOK。例えば「40代から始めたオーリー練習記録」といったシリーズにすれば、見てくれる人も応援してくれる人も自然と増えていきます。誰かの役に立つ情報になるかもしれませんし、自分自身の励みにもなります。
また、SNSで発信することで、「見られている意識」が良い意味でのプレッシャーになり、練習に対する集中力が高まることもあります。
「次の投稿では少し成長した姿を見せたい」と思えば、それがモチベーションになります。
発信内容はなんでもOK。トリックが成功した動画、練習中の失敗、使用しているデッキやシューズの紹介、スケートパーク訪問記など、“スケボーを楽しむ姿”そのものが、同じ趣味を持つ人たちにとって価値あるコンテンツになります。
インスタやYouTubeは、単なる「記録ツール」ではなく、つながりと成長を加速させてくれるツールです。ぜひ気負わず、楽しみながらチャレンジしてみてください。
あなたのスケボーライフが、もっと充実し、もっと広がるはずです。
コミュニティに入って仲間と楽しむコツ
スケボーは一人でもできる趣味ですが、仲間と一緒に楽しむことで何倍も面白くなるスポーツです。特に40〜50代から始めた方にとって、同じ世代のスケーターとのつながりは、大きなモチベーションになります。
最近では、インスタグラムやFacebookなどのSNSを通じて、#おじさんスケーター #スケボー好きと繋がりたいなどのハッシュタグから、同じ趣味の仲間を見つけやすくなっています。
コメントを残したり、練習動画に反応したりすることで、自然とつながりが広がっていきます。
また、地域のスケートパークやショップで定期的に開催されているスケートイベントや初心者講習会もおすすめです。
最初は少し勇気がいりますが、行ってみると「自分と同じように最近始めた」という仲間に出会えることも多いですよ。
コミュニティに入ることで得られるのは、情報やアドバイスだけではありません。「一緒に滑ろう!」という声がけがあれば、練習するきっかけが増え、自然とスケボーに向き合う時間も増えていきます。
また、仲間との会話から新しい技への挑戦意欲が湧いたり、互いの成長を喜び合えたりと、大人になってからの貴重な“刺激”と“つながり”を感じられるのも魅力です。
注意点としては、無理に人と比べすぎないこと。「あの人は上手いのに自分は…」ではなく、「自分は自分」と割り切って、マイペースに楽しむことが長続きの秘訣です。
一人で黙々と練習する時間も大切ですが、仲間と共有する時間は、それとはまた違った充実感があります。
スケボーをきっかけに広がる新しい人間関係も、おじさん世代にとっては心を豊かにする大切な要素です。
気軽に「はじめまして」と声をかけてみましょう。その一歩が、スケボーライフをもっと楽しく、もっと深くしてくれます。
良かったら僕の「Instagram」フォローしてください。
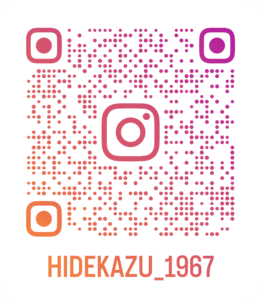
子どもや家族と一緒に楽しむスケボーの魅力
スケートボードは自分一人で楽しむのも最高ですが、子どもや家族と一緒に楽しめるという点も、大きな魅力のひとつです。
特に40〜50代のお父さんスケーターにとって、家族との時間を共有できる趣味があることは、とても貴重なことですよね。
子どもが「パパすごい!」と目を輝かせる姿を見たら、やっててよかったなと実感できるはず。逆に子どもにスケボーを教わる、なんていうのも、年齢に関係なく楽しめるスケートボードならではの風景です。
また、スケボーは公園や広場などのオープンスペースで楽しめるため、外でのびのびと遊ぶ機会を作るのにも最適です。
スマホやゲームでは得られない「生きた体験」を、親子で一緒に共有できるのは本当に素敵なことです。
一緒にスケートパークへ行ったり、デッキを選んだり、動画を撮って家で見返したり。そんな時間が、親子の絆を深める大切な思い出になります。
さらに、奥さんやパートナーも巻き込んでみるのも一つのアイデア。実際、最近ではママスケーターやファミリースケートを楽しむ人たちも増えていて、家族で一緒にスケボーを楽しむスタイルも注目されています。
もちろん無理に誘う必要はありませんが、楽しんで滑っている姿を見せるだけでも、きっと興味を持ってくれるはずです。
家族と一緒に笑い合いながら過ごす時間は、何にも代えがたい宝物。スケートボードというツールを通じて、そんな幸せなひとときをたくさん作っていきましょう。
「パパ、また一緒に滑ろうよ!」その一言が、きっとあなたのスケボーライフを何倍も豊かなものにしてくれるはずです。
よくある質問(Q&A)

ここまで読んで、「実際に練習するときはどうすればいいの?」「これって自分にもできるのかな?」と感じた方もいるかもしれません。
そんな疑問や不安にお応えするために、よくある質問とその答えをQ&A形式でまとめました。
これからオーリーに挑戦するうえで役立つ実践的なヒントが満載です。ぜひご自身の悩みに照らし合わせながらチェックしてみてください。
Q1. 止まって練習した方がいい?
A. はい。特に初心者や40〜50代の方は、まずは止まった状態でオーリーの基本動作を体に覚えさせることが大切です。慣れてきてから徐々に動きながらの練習に移行しましょう。
Q2. 何かに掴まって練習してもいい?
A. 初期段階ではアリです。掴まることで安心感が生まれ、動作の確認に集中しやすくなります。ただし、掴まりながらでは重心移動や上半身の使い方が身につきにくいため、徐々に手を離して練習しましょう。
Q3. オーリーの高さを上げるにはどうすれば?
A. 高さを上げたいなら、「障害物を飛ぶ練習」が効果的です。最初は割り箸や缶など低いものからスタートし、徐々に高さを上げていきましょう。オーリーバーやコーンを使うと、段階的に練習ができます。
Q4. オーリーの幅やステアはどうやって飛べばいい?
A. 幅を出すには、目線とスピードがカギです。目標物の頂点ではなく、着地点を見る意識で、やや前方へ蹴るようにオーリーしましょう。最初は小さな段差や溝から挑戦して、徐々に慣らしていくのがポイントです。
Q5. 後ろ足がうまく“寝ない”んだけど?
A. 無理に足を寝かせようとするのではなく、空中で前足をしっかり引きつけることで、自然と後ろ足も持ち上がってきます。重心をしっかり体の中心に保ち、空中での姿勢を安定させることが先決です。
まとめ|40~50代から始めるオーリーは“理論と楽しさ”が鍵!
いかがでしたか?この記事では、40〜50代からスケートボードに挑戦するおじさん世代の皆さんに向けて、オーリーの正しいやり方と練習法を徹底的に解説してきました。
オーリーの仕組みを理解し、テコの原理を活かして動作を分解。足の位置から空中での姿勢、そして着地まで、細かいステップを一つずつマスターすることで、初心者でも安全かつ効率的に上達できます。
また、練習方法やメンタル面のケア、モチベーションの維持法まで幅広く取り上げました。動画でのセルフチェックやSNSでの記録、家族とのスケボーライフの共有といった楽しみ方も紹介しました。
いくつになっても挑戦し続けるおじさんはかっこいいですよね。最初は不安や怖さがあっても、基礎をしっかり押さえ、少しずつ練習を積み重ねていけば、必ずデッキは浮き始めます。
そしてその瞬間から、あなたのスケボーライフはもっと自由で、もっと楽しくなります。
さあ、次はあなたの番です。今日から一歩踏み出して、“かっこいいおじさんスケーター”を目指してみましょう!



